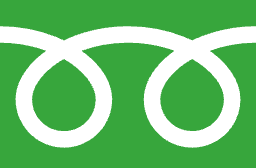- スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。まずは「ホームページを見た」とお伝えください。電話番号は0120-987-208です。

2020年の調査によると、日本国内で行われる葬儀の平均費用は149万3,624円とされています。万が一のことがあった際に、お葬式を執り行えるか不安な方も多いかもしれません。
「葬儀を安く済ませたい」「生活保護葬は聞いたことがあるけど、申請方法がわからない」という方のために、この記事では、費用や補助を受ける条件とともに、生活保護受給中のお葬式について解説します。

森畑 滋斗
【監修】森畑 滋斗
葛飾区を拠点とする葬儀社「シェア東京」の代表。厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター|京都グリーフケア協会 グリーフサポーター資格|葬儀業界での経験は17年に及ぶ。
お客様に寄り添った葬儀の提案だけでなく、専門知識をもとに葛飾区における葬儀に関する重要な情報やアドバイスをわかりやすく解説し、地域の方々に役立つ情報を提供しています。
生活保護葬とは
生活保護葬とは、経済的に困窮している個人や家族が故人を尊厳ある方法で送り出すことができるように、自治体が提供する葬儀支援制度です。この制度は、生活保護受給者はもちろん、一定の条件を満たす低所得者にも適用されることがあります。生活保護葬の主な目的は、経済的な困難があっても、すべての人が故人を尊重し、適切な葬儀を行うことができるように支援を提供することにあります。
生活保護葬の概要
一般的に、通常のお葬式では施主や喪主が葬儀費用を負担するのが一般的です。しかし、生活保護葬の場合は、費用負担なしでお葬式をあげられます。葬儀の形式や内容は制限されますが、葬祭扶助の範囲内なら負担なしでお葬式をあげられます。葬祭扶助を申請しないと、すべての費用を自費で支払うことになります。使用できる状況であれば、積極的に利用しましょう。
生活保護受給者の条件
生活保護葬の対象となるのは、主に以下のような人々です:
- 生活保護受給者:生活に困窮し、生活保護法に基づいた支援を受けている個人や家族。
- 低所得者:自治体が定める基準により、生活保護を受けていなくても、収入が非常に低く経済的に葬儀を行うことが困難な個人や家族。
故人が生活保護者でも親族に葬儀費用が出せる資産があるときには、葬祭扶助の対象外となるので注意が必要です。
実際は故人様が生活保護者でも、喪主が生活保護を受けてないと、葬儀費用はもらえないことがほとんどです。また、火葬費用は故人様が生活保護を受けていないと減免できません。
生活保護受給の範囲
生活保護葬によって支給されるサービスは、基本的に葬儀に必要な最低限の費用をカバーします。具体的には、以下のような費用が含まれることが一般的です:
- 葬儀の基本的なプランニングと実施費用
- 棺の提供
- 火葬費用
- 墓地、納骨堂使用料
- 逝去を告げるための最低限の告別式
申請の手順

葬祭扶助を申請する
祭扶助を受けるためには、所管の役所や福祉事務所に対して、葬祭扶助の申請を提出する必要があります。重要なのは、この申請を葬儀を行う前に完了させることです。
ただし、故人が生活保護を受けていたからといって、葬祭扶助が自動的に承認されるわけではないので、その点は留意が必要です。
- 葛飾区の場合
-
役所の保護課もしくは地域の福祉事務所に相談し、申請の手続きを行います。
東生活課相談係:〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
西生活課相談係:〒125-0042 葛飾区金町1-6-24(注釈)お住まいの区域により担当の課が異なります。
審査
申請をすると、葬祭費を出せる親族がいないか、故人が十分な貯蓄を遺していないかを確認し、葬祭扶助についての審査を行います。
葬儀社へ葬祭扶助を使うことを伝える
葬祭扶助の許可が下りたら、葬儀社に葬儀を依頼します。この時点で、葬祭扶助を使用する旨を葬儀社に明確に伝えることが重要です。事前に葬儀費用を支払ってしまうと、扶助金を受け取る資格を失う可能性があるため注意が必要です。
なお、役所が葬祭扶助に対応できる葬儀社を紹介してくれることもあるでしょう。葬儀社が確定したら、一般的な葬儀の準備と同じく、火葬のスケジュールや具体的な手続きについて打ち合わせを行います。
また、直葬に立ち会ってほしい人などにも連絡をして、葬儀の日時や火葬場の場所などを伝えましょう。
葬儀費用の支払い
葬儀の費用は、福祉事務所や市区町村の役所から葬儀社に直接支払われる。故人の預貯金や親族に支払い能力がある場合には、葬儀代に足りない料金分が補てんされます。
結果として、葬儀にかかった費用に対して、喪主や家族が直接支払う必要がある金額は0円となります。
注意点
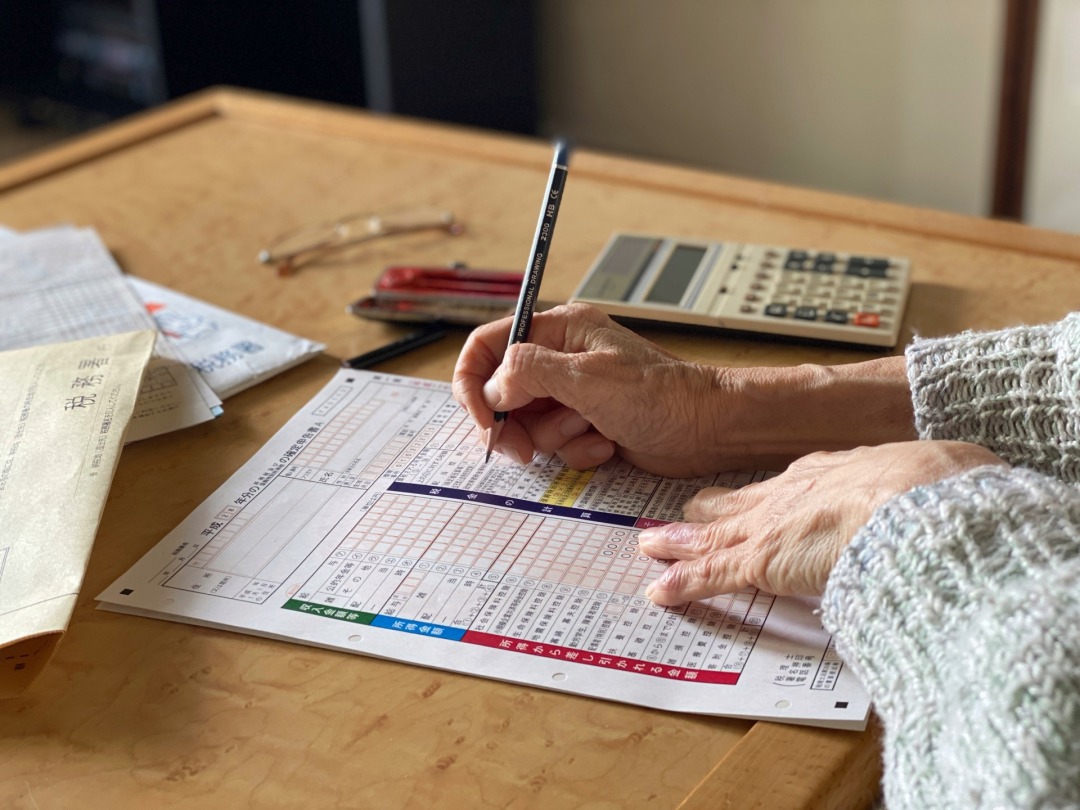
金額を超えないように
葬祭扶助による葬儀は、「直葬」という形式を採用します。これは通夜や告別式を伴わない、より簡素化された手続きで、遺体の輸送、その安置、棺への納め、火葬、そして遺骨を収集する一連の流れに沿って進められ、通常1日で完結します。この方法では、故人と親しかった少数の人々による静かなお別れが行われます。ただし、待機時間中に発生する椅子や部屋の使用料などの費用は、個人の負担になる点に注意が必要です。
戒名はない
通常の直葬プロセスでは、棺を出す際や火葬を行う前に、僧侶による読経が含まれます。しかし、国の補助を受ける場合、その費用でお布施をカバーすることはできないため、読経や戒名の授与は行われません。遺体を火葬場へ運んだ後、集まった人々が黙祷を捧げると、火葬が開始されます。火葬が終わると、遺骨を骨壺に納める骨上げ作業を経て、その場は解散となります。
まとめ
生活保護受給者が亡なられて、その親族や関係者が葬儀のための金銭的負担が困難な場合は、自治体から葬祭扶助を受けることができます。突然のことになるとわからないことも多いかと思いますので、身近に生活保護受給者がいる場合は、この制度や扶助してもらえる内容、手続きの流れなどを把握しておきましょう。
24時間 / 365日受付中
- スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。まずは「ホームページを見て、葬祭日補助金について相談したい」とお伝えいただけるとスムーズにご案内が可能です。